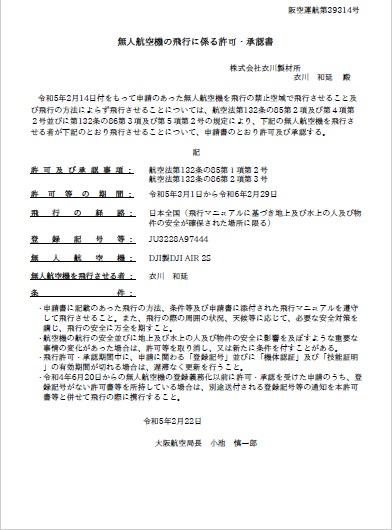スタッフBLOG
「先進的窓リノベ事業」
2023年 07月 11日 (火) 09:56
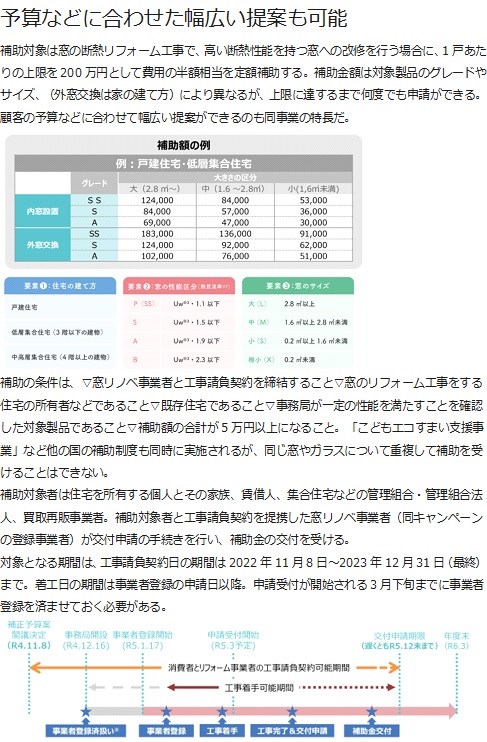
家選びの基準変わります
2023年 05月 15日 (月) 14:10
家選びの基準変わります
耐震だけじゃダメ!
これからは、省エネ住宅が標準になる「ZEH」
2025年には今の省エネ住宅が最低ラインになって
さらに、2030年にはその最低基準がZET水準の省エネ住宅になる
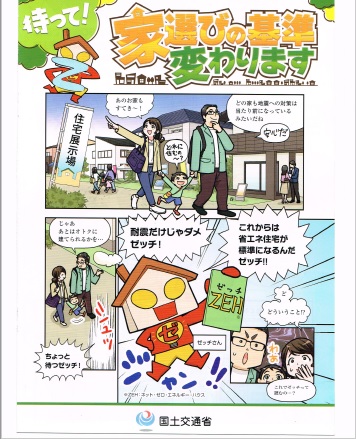

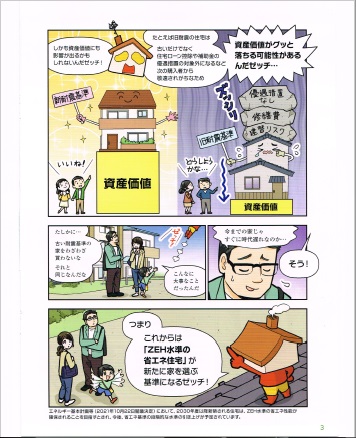
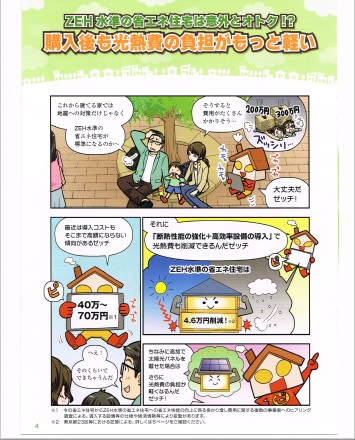
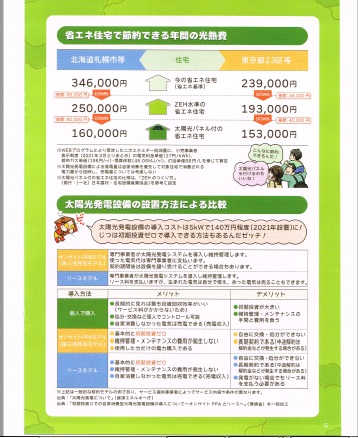
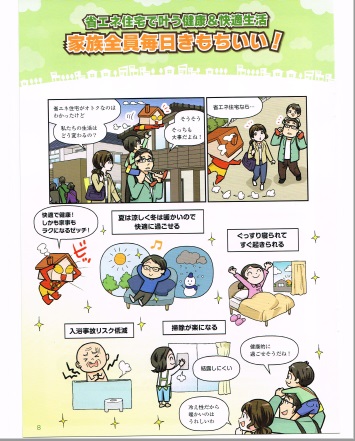
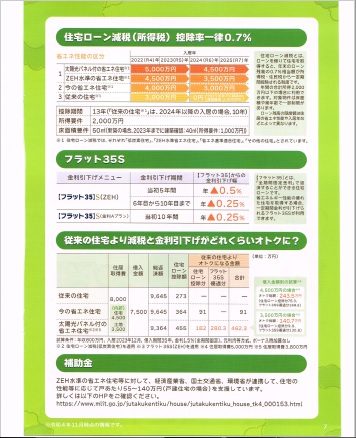
無人航空機飛行許可・承認書
2023年 03月 14日 (火) 10:06
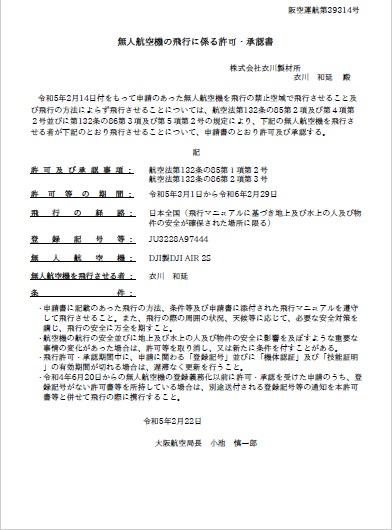
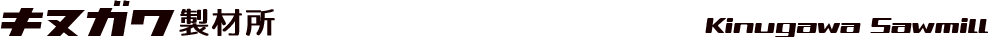
2023年 07月 11日 (火) 09:56
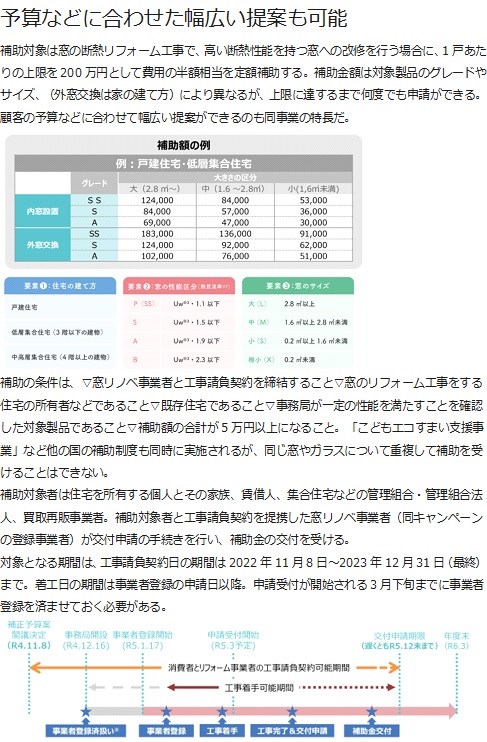
2023年 05月 15日 (月) 14:10
家選びの基準変わります
耐震だけじゃダメ!
これからは、省エネ住宅が標準になる「ZEH」
2025年には今の省エネ住宅が最低ラインになって
さらに、2030年にはその最低基準がZET水準の省エネ住宅になる
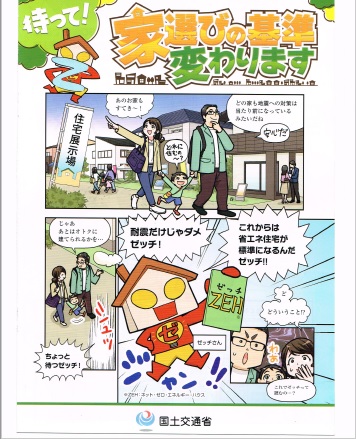

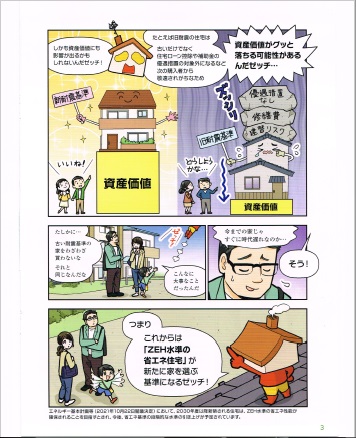
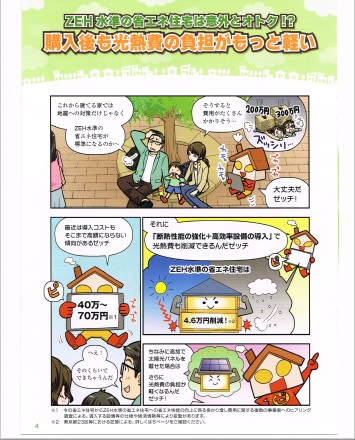
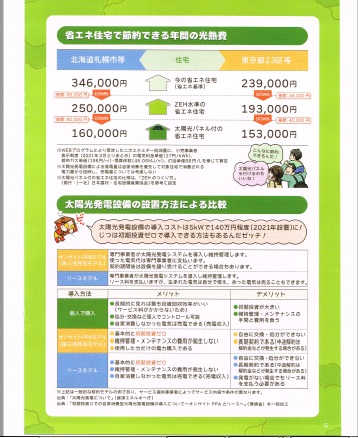
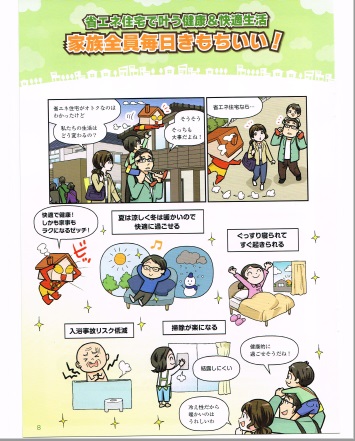
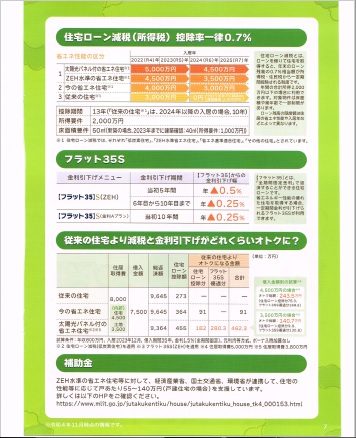
2023年 03月 14日 (火) 10:06